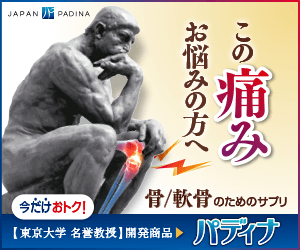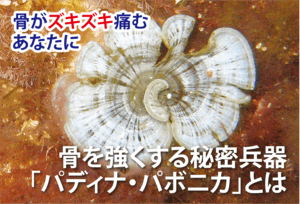骨と糖尿病の関係とは

骨と糖尿病の切っても切れない関係とは
「骨と糖尿病には深い関係がある」と言われたら、あなたは「ピン!」ときますか?
あまりピンときませんよね。
骨と糖尿病に関係があるなんて、聞いたこともない方が多いのではないでしょうか。
一般に、「骨」といえば、カルシウム。
「糖尿病」といえば、糖分の摂りすぎ、血糖値が高い、肥満など…。
このようなことが思い浮かびますよね。
一体、これらのどこに関係があるのでしょうか?
今回は、骨と糖尿病の関係について紹介します。
糖尿病といえば、知人からこんな話を聞いたことがあります。
知人のお父様(当時53歳)が、ある日突然倒れてしまいました。
以前から、立ちくらみや目まい、疲れが激しく、年齢的なものかと思っていました。
しかし、倒れたことを機に検査をしたところ、なんと糖尿病と診断。
幸い病状は軽かったので、深刻になることはなく、入院は免れました。
お父様は、医者から食事療法と「あること」をするように指導されました。
それは「毎日犬の散歩をすること」でした。
そのアドバイスを忠実に守り、お父様の症状はみるみるうちに回復していきました。
いまは多少の食事制限をしているものの、お酒もたしなめるほどになりました。
なぜ、散歩するだけでこんなに糖尿病が改善したのでしょうか?
糖尿病予備軍に「歩け」という理由

このように、糖尿病の改善策として、医者から「歩きましょう」と指導されることがあります。
糖尿病の原因は、糖分過多、カロリーオーバー、運動不足などにあるといわれています。
このことから、症状を改善する方法の1つとして、歩くことで代謝を上げ、カロリーを消費することが勧められているのです。
確かに、歩いたり、軽い運動をしたりすることは、糖尿病の改善につながることはうなづけます。
しかし、それだけではありません。
実は、糖尿病の改善につながる要因が、他にもあったのです。
新しく見つかった骨の役割
骨の主な役割は、体を支えること。
その他にも、内臓を保護する、カルシウムを貯蔵する、血液をつくるなどのさまざまな働きがあります。
骨の役割
骨は体重の約15〜18%を占め、全身には206個の骨があります。
主な役割は、次のとおりです。
(1)体を支える
人の体は、206個もの骨の組み合わせで支えられています。
(2)動けるようにする
筋肉と協力して、立ったり歩いたりといった運動をする働きがあります。
(3)体の器官を保護する
心臓や肺などの大切な臓器を守ります。
(4)血液をつくる
赤血球、白血球、血小板などをつくります。
(5)カルシウムなどミネラルの貯蔵
カルシウムなどのミネラルを貯めておく働きがあります。


(参考:中外製薬 https://chugai-pharm.info/medicine/karada/karada018.html#karada18_anch03 )
そしていま、世界中の研究者に注目されているのが、骨から分泌される「骨ホルモン」。
なんと、骨にもホルモンがあったんです。
この骨ホルモンにも、意外な働きが発見されました。
骨にもホルモンがあった!
骨から分泌されるホルモン、その名も「オステオカルシン」。
この骨ホルモンは、骨を上手に刺激すると、骨から大量に放出されます。
やがて全身へ運ばれ、脳、肝臓、すい臓、腎臓など全身の臓器を活性化します。
しかも、骨ホルモンは血糖値を下げるという実験結果も。
骨ホルモンは、糖分抑制に効果があることがわかってきたんです。
(参考:雑誌「NHKガッテン!(夏)」Vol.35)
骨の本当の役割
このように、骨はわたしたちの体を支えるだけでなく、全身の臓器も元気にしていたんですね。
さらには、骨ホルモンが血糖値を下げてくれることもわかりました。
骨ホルモンは、骨をうまく刺激することで放出されます。
つまり、歩いたり、軽い運動をしたりして、適度に骨を刺激することがポイント。
先ほど、糖尿病になった知人のお父様の話をしました。
お父様は、医者のアドバイスを守って毎日犬の散歩をしたところ、症状が改善しました。
これは単に、「歩いたらカロリーが消費されて糖尿病がよくなった」というだけではありません。
「歩くことで骨が刺激され、骨ホルモンが分泌されたことで、血糖値が下がった」ともいえるでしょう。
お父様の症状が改善されたのも納得ですね。
1日1分でできる!ラクちん健康法
「歩く」以外にも、骨ホルモンを分泌させる簡単な運動があります。
それは、雑誌NHKガッテン!でも紹介された「かかと落とし」健康法。
やり方はとっても簡単!
「かかと落とし」のやり方
(1)軽く足を開いて、姿勢よく立ちます。
(2)ゆっくり大きく真上に伸び上がり、つま先立ちをします。
(3)ストンと一気にかかとを地面に落とします。

続けてやらなくても、何回かに分けてやってもOK。
1日の合計が30回以上を目指しましょう。
注意:関節に疾患のある方、骨粗しょう症の方、ご高齢の方などは、運動の前に医師と相談してください。
また、転倒の可能性がある場合はお控えください。
(参考:ガッテン! http://www9.nhk.or.jp/gatten/articles/20170215/index.html )
いかがでしたか?
骨と糖尿病は、切っても切れない密接な関係があるんですね。
骨を丈夫にすることは、折れにくい強い骨になるだけでなく、全身の臓器も元気になるということ。
適度な運動で骨ホルモンを分泌させれば、糖尿病の予防や改善にもなるでしょう。
骨から健康にすることで、体全体を健康にしていきましょう。